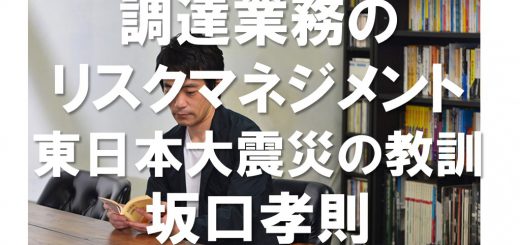調達業務のリスクマネジメント~東日本大震災の教訓 1章(2)-5
そのころ兵庫県明石のオフィスで働いていた神野スミエは、インターネットを活用した情報収集を進めていた。神野も、もちろん営業窓口経由の情報収集は進めていた。ただし、同時に注目したのはホームページの新着情報だった。多くのバイヤーは営業マンに連絡をとる。しかし、それでは、ティア2以下のメーカーの情報を把握することは難しい。ただ、神野はあらかじめ用意していた調達品に使われている原材料メーカーリストによって、各社のホームページを回覧していた。生産状況がよくわかった。しかも、そうしておくと、ティア1サプライヤーと会話をするときも整合性が保てる。「震災時に公開情報であってもいかに素早く収集するかが問われる」と神野は感じていた。
茨城県・つくば市のオフィスで働く佐藤貴史(仮名)は、一つの問題に直面していた。それは営業マンから情報がなかなか吸い出せないことだ。営業マンが自社の状況についてまったく把握していなかったわけではない。ただ、「いつくらいから生産復旧できそうか」と問うと、「それは答えられない」と返ってくる。佐藤は、営業マンの立場として一度言ってしまったものを取り消すことができないと恐れているのではないか、と感じた。佐藤は方針を変え「ここで○○日から生産復旧できるからといって、それを揚げ足取りには使わない。とにかく状況を知りたいから、教えてくれ」と伝えた。佐藤はそこから少しずつ状況を把握することになった。営業マンも客先に不確かなことをいってしまっては責任問題に発展する。本来は、震災下でこそバイヤー企業とサプライヤーが団結して状況の打破に動かねばならない。ただし、このような状況であっても、まだ心理的な壁があるのか。佐藤は日頃のサプライヤーマネジメントについて想いを巡らせていた。